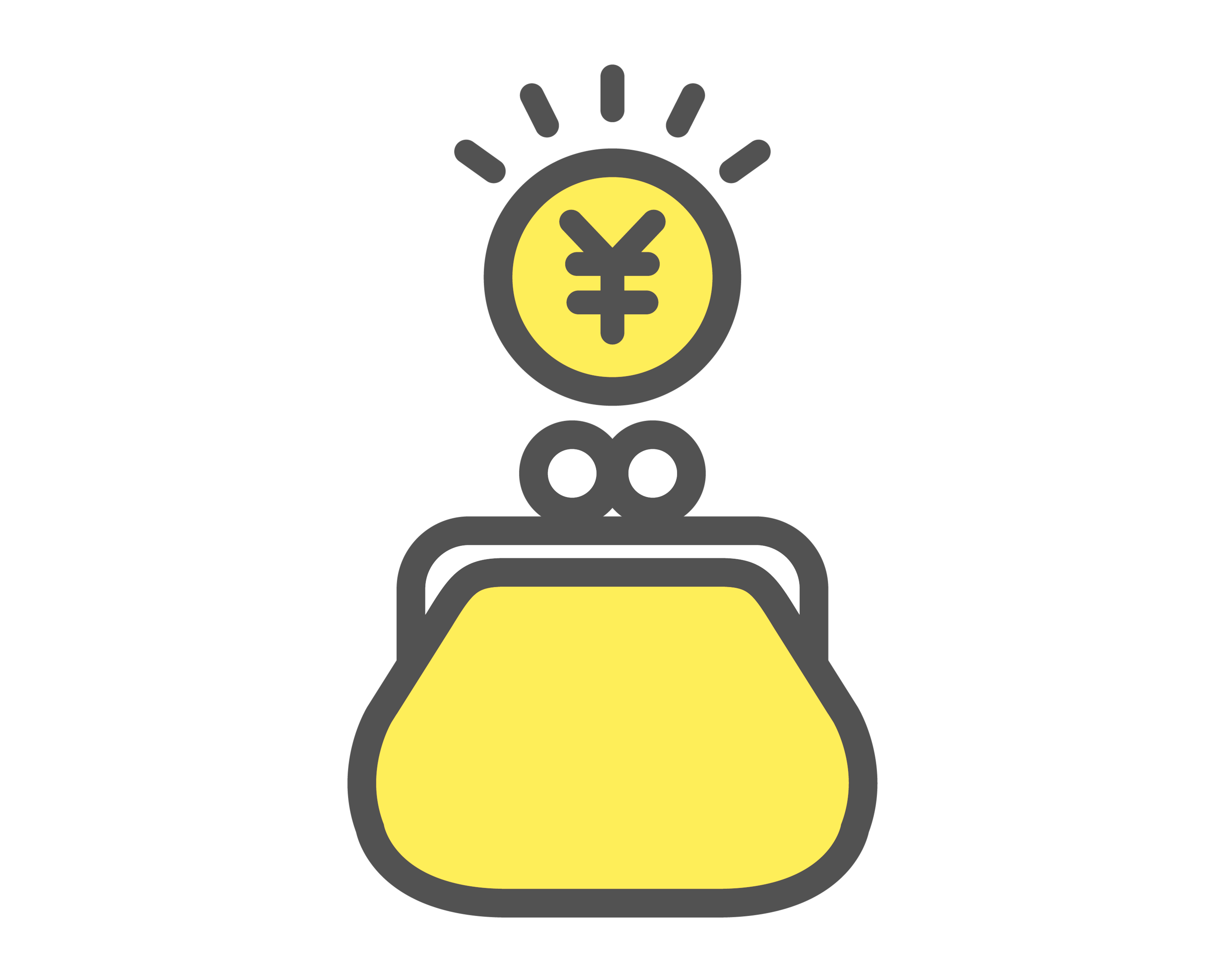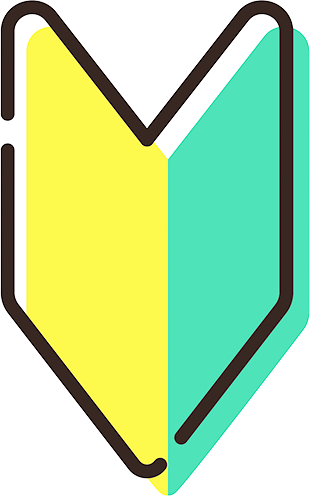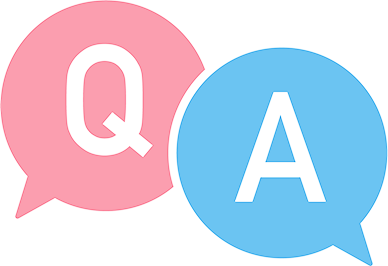上と比較して落ち込んでしまう人に。~名古屋心療内科コラム

◆ 比べることで、落ち込む心
「上には上がいる」と思うのは、人として自然なことです。
仕事ができる人、才能にあふれた人、努力を惜しまない人——。
そうした存在を見ると、刺激を受ける反面、
「自分なんてまだまだだ」と落ち込んでしまうこともありますよね。
心理学では、こうした他人との比較を「社会的比較理論(Social Comparison Theory)」と呼びます。
アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した理論で、
人は自分の価値や能力を測るために、無意識に他人と比べてしまうのです。
◆ 上方比較と下方比較
比較には2種類あります。
ひとつは、自分より上の人と比べる「上方比較(Upward Comparison)」。
もうひとつは、自分より下の人と比べる「下方比較(Downward Comparison)」です。
上方比較は、モチベーションを高めるきっかけになりますが、
同時に「自分は劣っている」と感じやすく、
自己肯定感を下げるリスクもあります。
一方で下方比較は、「自分はまだ大丈夫」と安心を得る効果があります。
もちろん、他人を見下すことを推奨するわけではありません。
でも、心が疲れているときには、この“ちょっと下を見る”視点が、
自分を守る優しいクッションになることもあるのです。
◆ 「下には下がいる」で心をゆるめる
たとえば、仕事でミスをしたとき。
「自分なんてダメだ」と責めるより、
「まぁ、世の中にはもっと失敗してる人もいるし」と思う方が、
心の立て直しは早くなります。
それは現実逃避ではなく、回復のための視点の切り替えです。
常に上を見て苦しくなるより、
一度視線を下げて「自分もよくやってる」と思う方が、
次の一歩を踏み出しやすくなります。
◆ 比べる対象を“自分”に戻す
とはいえ、いつまでも「下を見て安心」ばかりでは、成長が止まってしまう。
だからこそ、最終的には“昨日の自分”と比べることが大切です。
上も下も、外ではなく内に戻す。
「少しでも前に進めた自分」を認めていくことが、
健やかな比較の使い方です。
◆ まとめ:比べるのではなく、癒やすために使う
「上には上がいる」と思うと、努力の糧になる反面、疲れる。
そんなときは「下には下がいる」と思って、
少し肩の力を抜きましょう。
それは、他人を下に見るためではなく、
自分を責めないための優しい工夫です。
今回の話、何か少しでも参考になることがあれば幸いです。
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました。
(完)