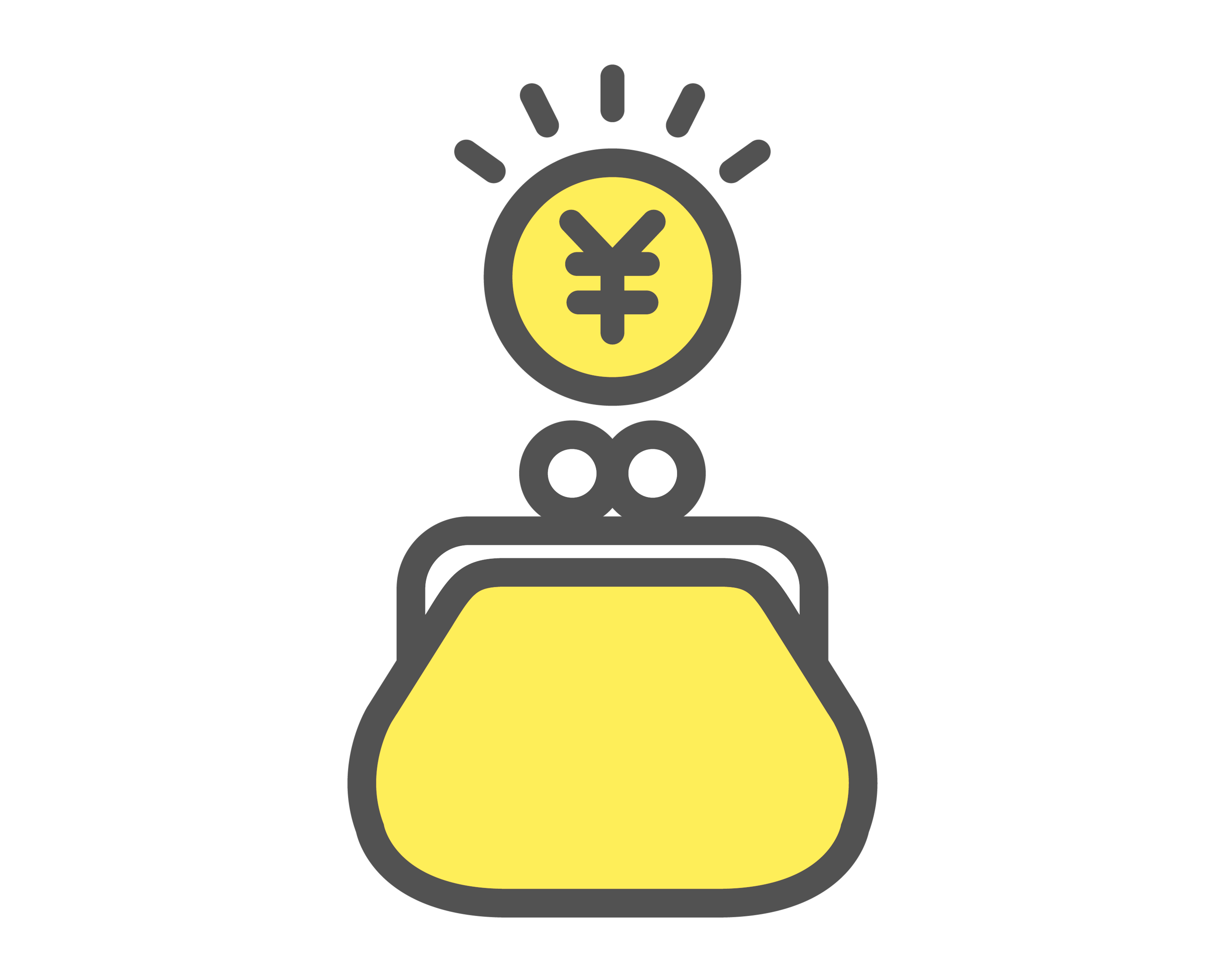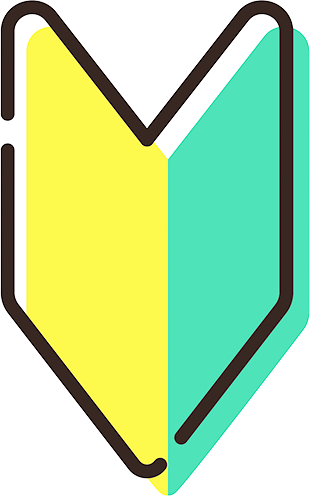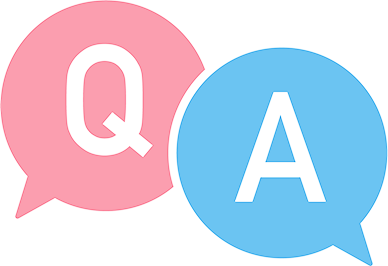恨みを抱いたときの考え方。~名古屋診療内科コラム

◆ 恨みは「毒」のように自分をむしばむ
誰かにひどいことをされた。
許せない言葉を言われた。
その痛みが心に残って、「どうしても忘れられない」というとき、人はつい恨みの感情を抱いてしまいます。
でもその恨みをずっと握りしめていると、
少しずつ自分の心がすり減っていくのを感じませんか?
心理学にはこんな有名な言葉があります。
「誰かを恨み続けるのは、毒を飲みながら相手が死ぬのを待つようなもの」
つまり、恨みは相手を傷つけるどころか、
自分の心と体にダメージを与えていくんです。
◆ 恨みの正体は、「傷ついた心の防衛」
恨みという感情の根底には、「理不尽に傷つけられた」という痛みがあります。
本来なら、悲しみとして処理されるべき感情を、
人は「怒り」や「憎しみ」に変換することで、自分を守ろうとします。
心理学ではこれを防衛機制の一種とみなします。
つまり、恨みは「心が壊れないようにするための一時的な盾」。
けれど、その盾を長く持ち続けていると、
本来の“回復のチャンス”を失ってしまうのです。
◆ 許すことは「相手のため」ではなく「自分のため」
「許すなんてできない」と思うのは当然です。
でも、“許す”とは、加害者を肯定することではありません。
むしろ、「もうこれ以上、自分の心をその人に支配されないようにする」
という自分のための解放行為なんです。
心理学者フレデリック・ルスキンは、
「Forgive for Good(よく生きるための許し)」という研究で、
恨みを手放した人ほどストレスホルモンが減少し、
幸福感や免疫力が上がることを明らかにしました。
つまり、“許す”とは「相手を救うこと」ではなく、
「自分を救い出す」ことなのです。
◆ 恨みを手放すための小さなステップ
いきなり完全に許そうとする必要はありません。
まずは、少しずつ自分のエネルギーを「恨み」から「回復」に戻していきましょう。
たとえば——
- 恨みの気持ちが浮かんだら、「これは私を守ってくれていた感情だ」と受け入れる
- 「あの人のせいで」ではなく、「今、自分がどうしたいか」に焦点を移す
- 「もうこの痛みから自由になりたい」と言葉に出してみる
それだけでも、心の中で小さな変化が始まります。
◆ まとめ
誰かを憎む気持ちは、人間として自然な反応です。
でも、それを四六時中抱えていると、
一番苦しむのは、自分自身です。
その毒を飲み続けなくてよくなるよう
少しずつでいいから、手放していきましょう。
今回の話、何か少しでも参考になることがあれば幸いです。
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました。
(完)