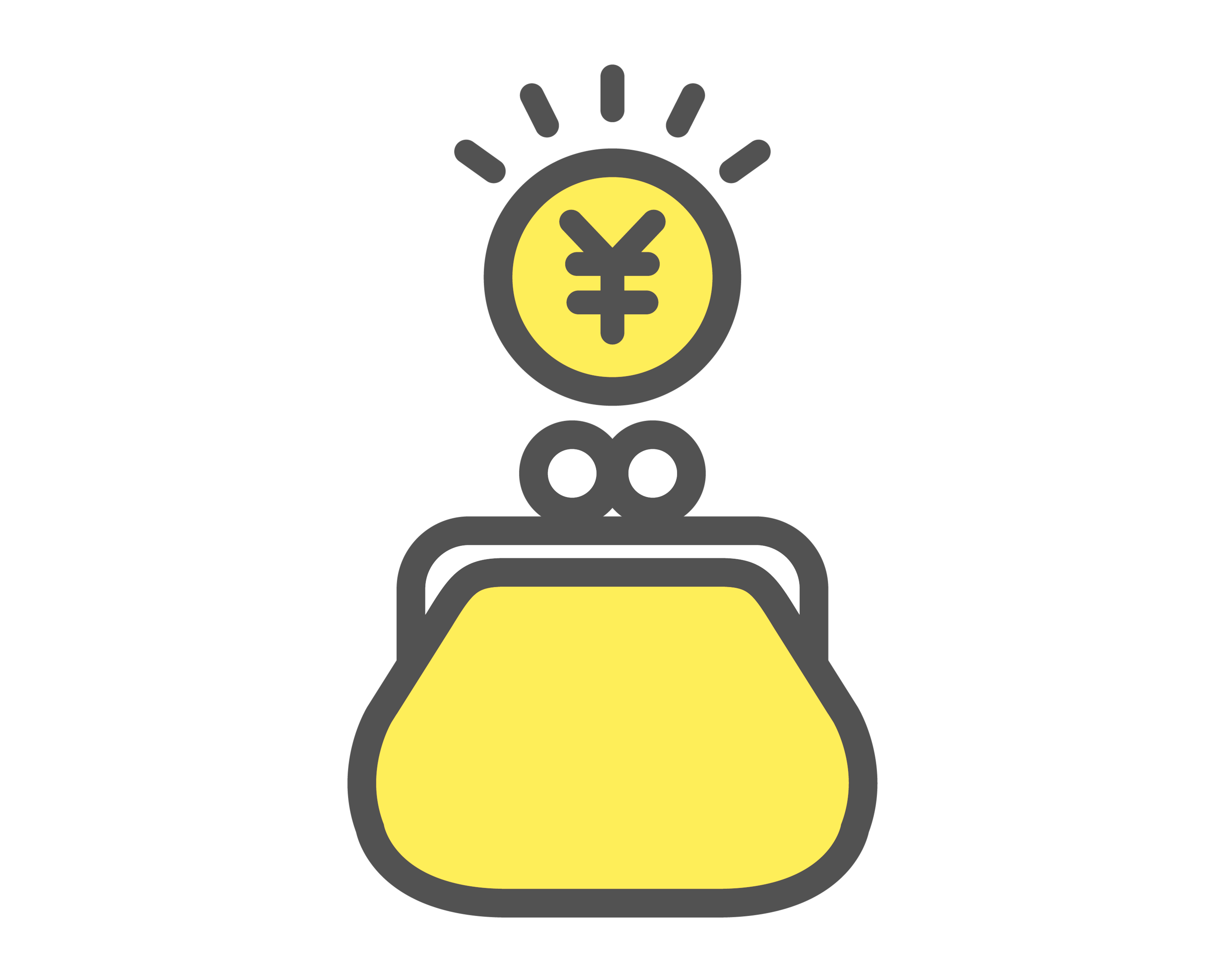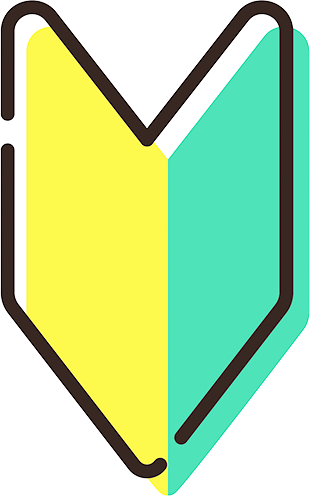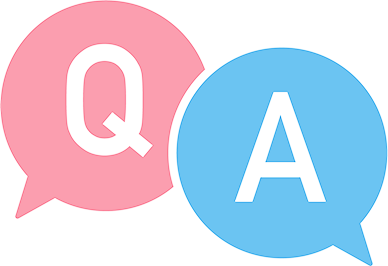発達障害と二次障害
発達障害と二次障害
グレーゾーンの方も知っておきたい原因と予防法
【医師が解説】
「自分は発達障害(グレーゾーン)かもしれない」「身近な人への対応に悩んでいる」方へ。
二次障害が起こる背景と予防のポイントを、わかりやすく解説します。

要点
- 発達障害は良し悪しではなく「特性」。困りごとは環境とのミスマッチで生じやすい
- ミスマッチが続くとうつ・不安・自己否定感などの二次障害につながる
- 本人の特性に合う環境調整・周囲の理解・専門的サポートで二次障害は予防しやすい
こんにちは、ゆうメンタルクリニック医師の森しほです。
今日は発達障害と二次障害についてお話しします。
SNSなどで「発達障害の人には素晴らしい才能がある」という投稿を見かける一方で、卑下するような表現もあります。
ですが、発達障害は本来“良い・悪い”で判断するものではなく、一人ひとりの特性です。
ただし、特性と周囲の環境が合っていないとき、学校・職場・家庭で「困りごと」が起こりやすくなります。
例えば、集中が続かず指摘が増える、ペースのズレで人間関係がぎくしゃくする——こうしたミスマッチが続くと、強いストレスが積み重なり、うつ症状・不安症状・自己否定感の高まりなどの「二次障害」につながることがあります。
一方で、本人の特性に合った配慮があり、「受け入れられている」と感じられる環境では、二次障害は起こりにくいと考えられています。
環境調整(見通しを伝える、感覚刺激を減らす、タスクを小分けにする等)や、周囲の理解、医療・カウンセリングなどの専門的サポートは、負担を軽くし、日常生活の「やりやすさ」を育てます。
つまり——「発達障害=問題」ではなく、「環境との相性」が鍵です。
ひとりで抱え込まず、気になるサインがあれば早めに相談してみてくださいね。
\ 簡単1分 /
二次障害の傾向チェック
当院では、医師による診察だけでなく、心理士によるカウンセリングも行っています。