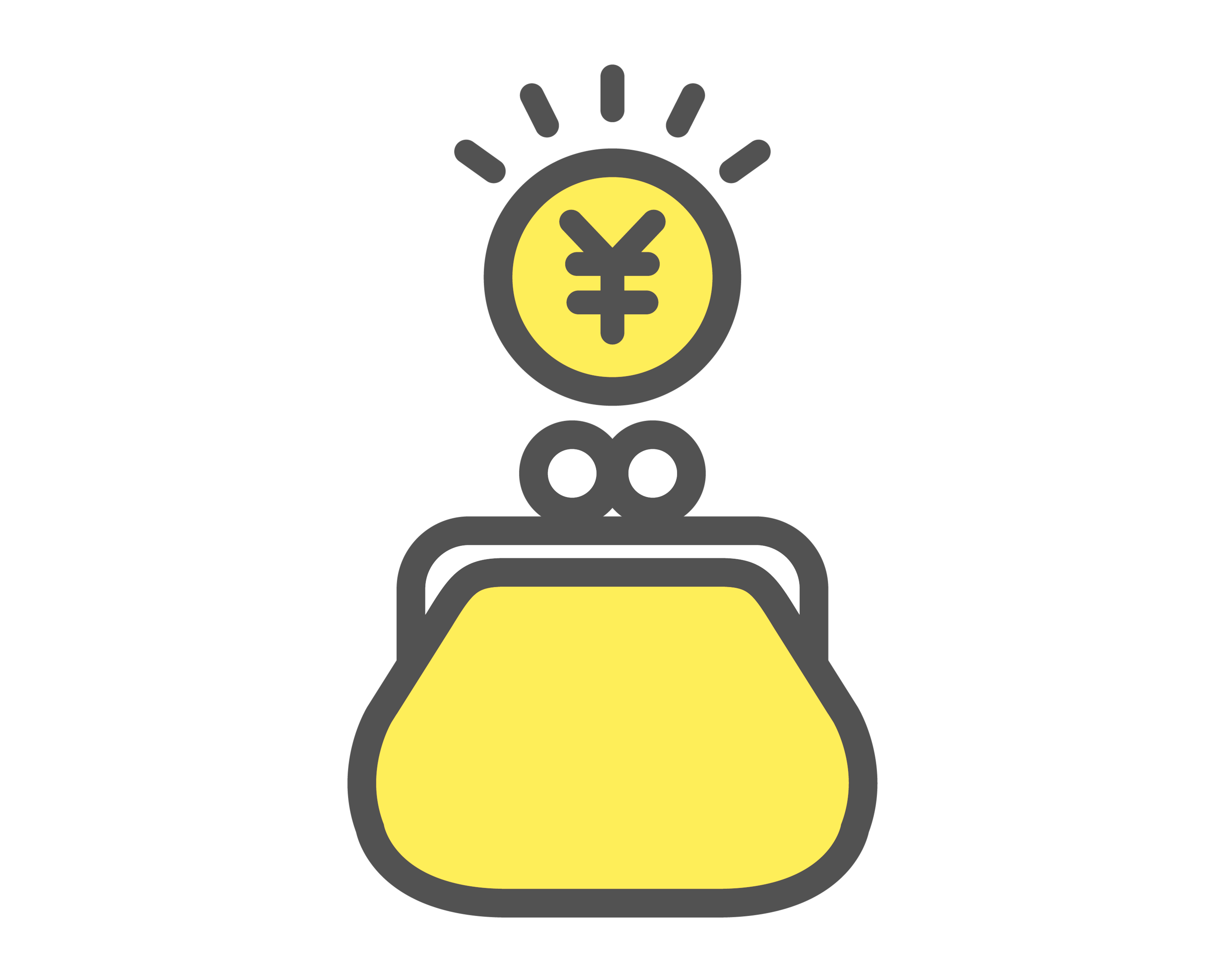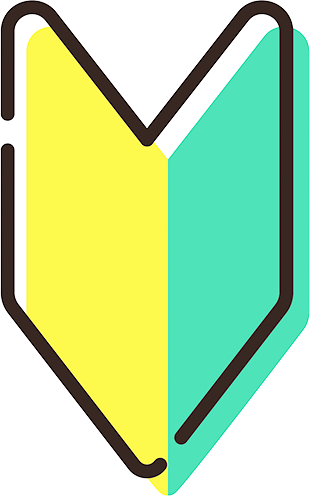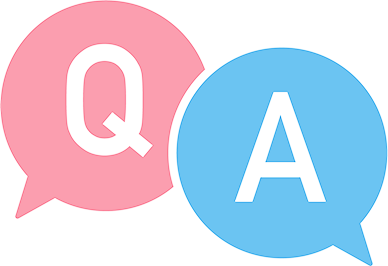HSP(超敏感な人)の診断基準~名古屋心療内科マンガ
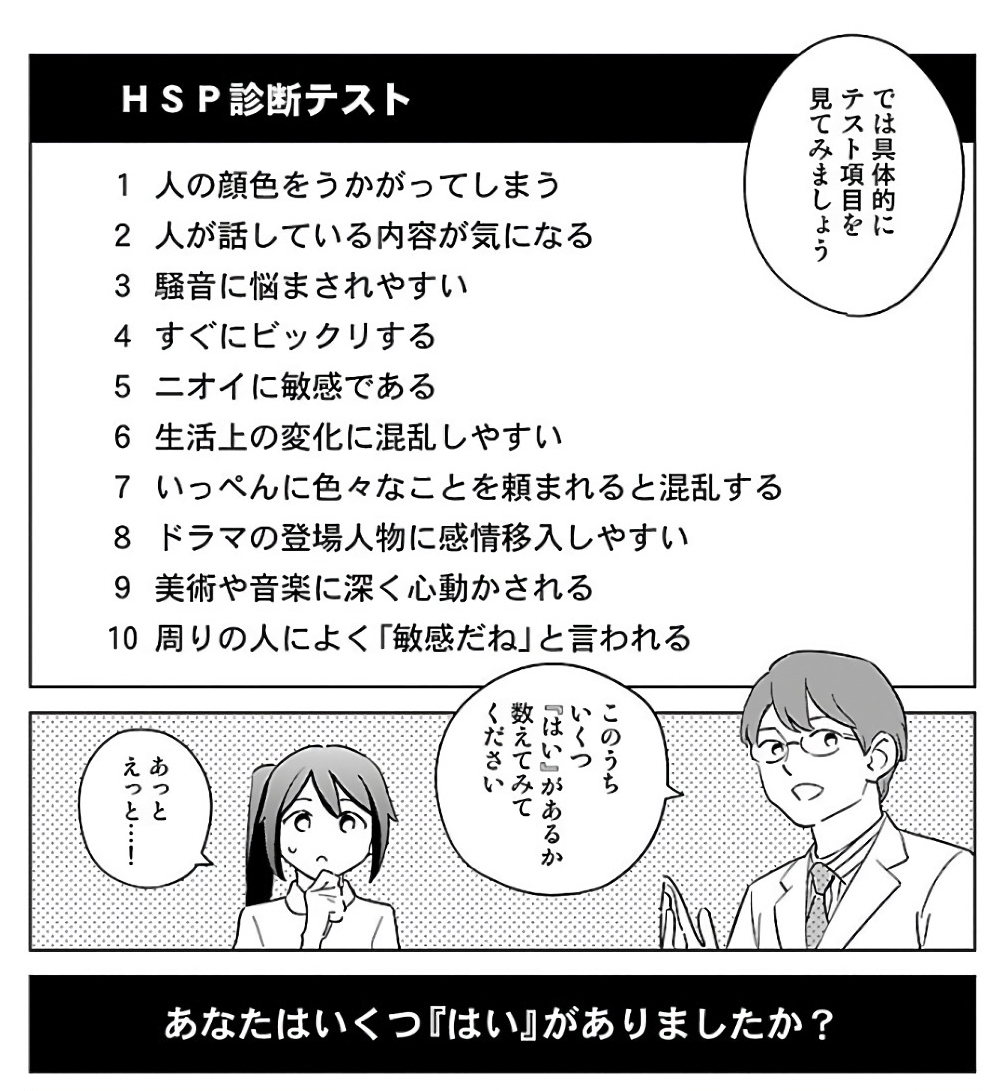

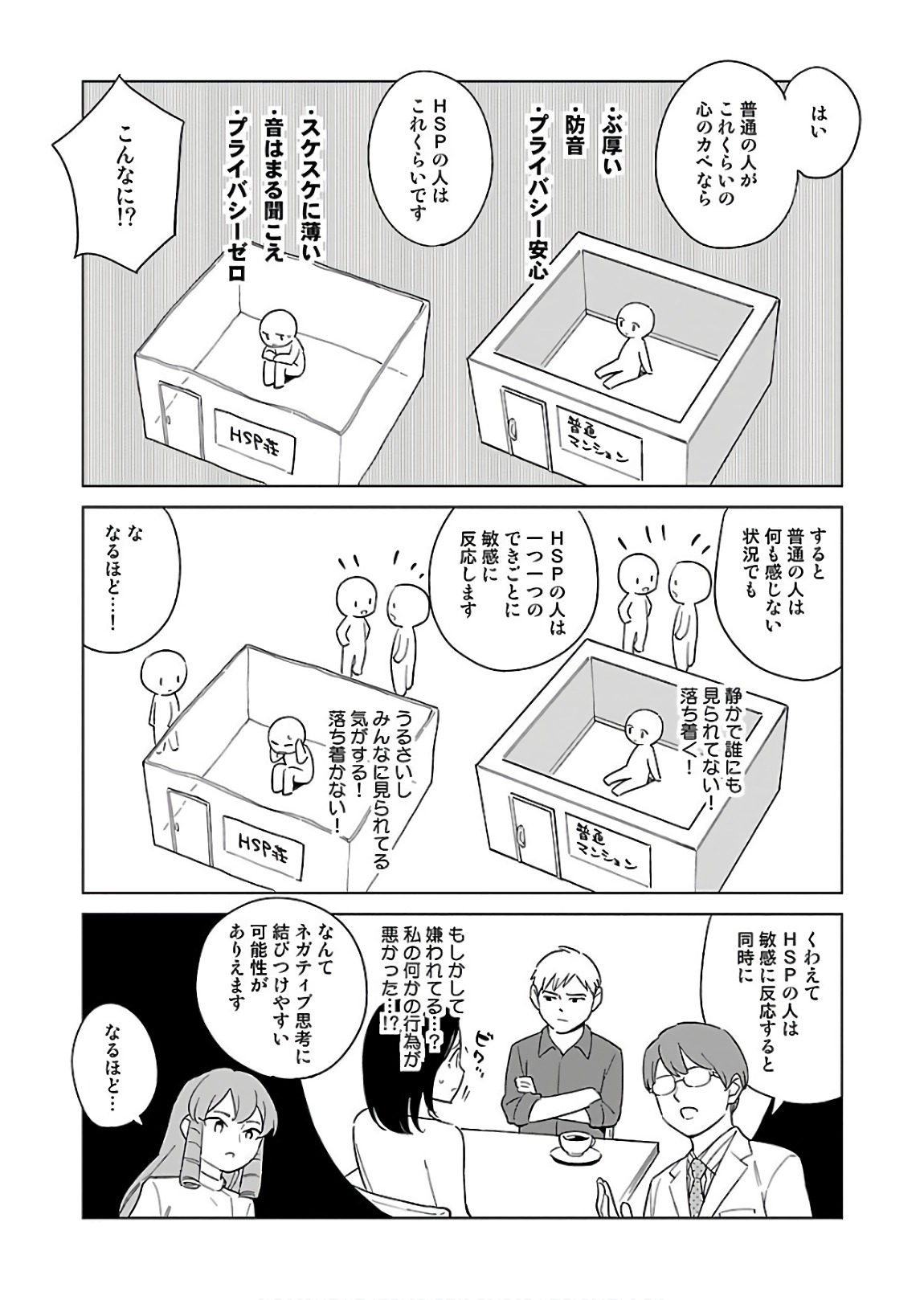

目次
◆ HSPとは?
HSPとは「Highly Sensitive Person(とても敏感な人)」の略。
アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念で、人口の約15〜20%が当てはまるとされる性格傾向です。
特徴としては…
- 人の気分や表情の変化にすぐ気づく
- 大きな音や強い光が苦手
- ちょっとした失敗を長く引きずる
- 他人の感情に強く共感しやすい
こうした性質から、日常生活で「生きづらさ」を感じやすい人が多いのです。
◆ HSP傾向のある人の体験
たとえばあるHSP傾向のある女性は、職場で上司の表情が曇っただけで「自分が怒らせたのでは?」と気になって眠れなくなったと言います。
また別の男性は、飲み会の大きな声やざわつきで強い疲労感を覚え、翌日まで気分が沈んでしまいました。
こうしたエピソードは、まさにHSPの特徴に合致します。
◆ HSPは「障害」ではない
ここで大切なのは、HSPは「病気」や「診断名」ではなく、あくまで性格傾向であるという点です。
心理学的には「刺激に対して敏感に反応しやすい気質」と説明されます。
つまり「繊細なアンテナを持っている人」というだけで、必ずしも問題ではありません。
むしろ研究によれば、HSPの人は創造性や共感力、注意深さに優れている傾向もあり、芸術家やカウンセラー、教師などに多いとも言われています。
◆ 注意すべきは「敏感さ」より「疲労」
問題となるのは、HSPであること自体ではなく、それによって生活に支障が出るかどうかです。
例えば…
- 人間関係の悩みで夜眠れない
- 仕事のストレスを過度に抱え込み、体調を崩す
- 自分を責め続けて気分が落ち込む
こうした場合、単なる「繊細さ」では済まず、うつ病や不安障害につながることもあります。
◆ HSPとのつきあい方
思い当たることがあれば、こんな手法を試してみましょう。
- 刺激を減らす環境調整
イヤホンで音を和らげる、照明を落とすなど物理的に刺激を減らす。 - 「考えすぎ」を客観視する
認知行動療法でも使われる「本当にそうかな?」という視点を持つ。 - 休息のルーティンを作る
読書や散歩など、自分をリセットできる習慣を日常に入れる。
◆ 結論:気にしすぎなくて大丈夫。でも気になるなら専門へ
HSPは「特別な気質」ではあっても「病気」ではありません。
「自分は繊細だからダメだ」と思う必要はないのです。
ただし、その敏感さが 生活や仕事に支障をきたすレベルで続いている場合 は、早めに当院にご相談ください。
心理士や医師が「気質」と「病気」を区別しながら、適切なアドバイスやサポートをします。
今回の話、何か少しでも参考になることがあれば幸いです。
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました。
(完)